knowledge ナレッジ
KPI設計とは?マーケティング成果を生み出す実践フレームを解説

「戦略は立てたけれど、現場でうまく進んでいない」「目標はあるのに、日々の業務と結びついていない」──そんな課題の多くは、KPI(重要業績評価指標)の設計不足に起因しています。
KPIは、目標達成に向けて組織が取るべき行動と進捗を“見える化”する羅針盤のような存在です。ただし、単に数値を並べるだけでは意味がなく、目的に紐づいた設計と現場で活きる運用体制がなければ、機能しません。
本記事では、KPIの定義と設計ステップ、ありがちな失敗とその回避策、さらに弊社Oz linkが実践する設計手法やマーケティング領域での活用事例までを体系的に解説します。
Contents
KPI設計とは?定義と目的をわかりやすく整理
KPI設計は、戦略を実行に移し、成果に変えるための橋渡しです。
「何をもって成果とするか」「どのプロセスに注目すべきか」を明らかにすることで、目標達成の精度とスピードを高めます。
ここでは、KPIの基本的な定義や、KGIとの違い、そして設計する目的をわかりやすく整理します。
KPIとは何か?KGIとの違いと関係性
KPI(Key Performance Indicator)とは、重要業績評価指標のことを指します。
企業やプロジェクトが掲げる目標(KGI=Key Goal Indicator)に対して、その達成状況を判断するための中間指標です。
■KGI:最終的なゴール(例:年間売上10億円)
■KPI:その達成に向けた途中の評価軸(例:月間新規顧客数/CV数)
つまり、KPIは“目標達成に向けた途中経過を見える化する数値”であり、戦略実行の進捗や質を測るために不可欠な要素なのです。
KPIを設計する目的と役割
KPIを設計する主な目的は、「目標達成に向けた行動やプロセスを、具体的かつ継続的にモニタリングできるようにすること」です。
単に目標を掲げただけでは、何から着手すべきか、どこに問題があるのかが見えません。KPIを設計することで、以下のような効果が得られます。
■チーム内での認識合わせ(何を重視すべきか)
■日々の行動や施策の優先順位が明確になる
■施策の効果検証と改善サイクルが回る
KPIは、戦略を行動に変換する“実行の設計図”とも言える存在です。
なぜ「設計する」ことが重要なのか
KPIは、やみくもに設定しても意味がありません。重要なのは、「戦略に紐づき、現場で運用できるKPI」を設計することです。
たとえば、マーケティング部門が「SNSフォロワー数」をKPIとした場合、それが売上やCVにどう貢献しているのかが曖昧では、行動の優先順位がずれてしまいます。
【目的 → 戦略 → 施策 → KPI】という一貫性の中で設計されていること。そして、現場の行動を促す指標として“解像度高く使えるか”が鍵となります。
KPI設計の基本ステップと考え方
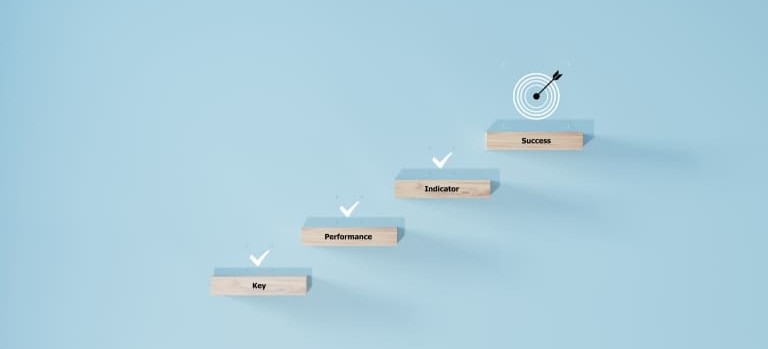
KPIは、ただ数字を設定するのではなく、目標達成までのプロセスを分解し、実行可能な形で指標化することが重要です。
ここでは、KPI設計の基本ステップを紹介します。
STEP1:KGI・目的の明確化
すべてのKPI設計は、「最終的に何を達成したいのか?」というKGI(Key Goal Indicator)=目的の明確化から始まります。
■売上拡大を目指すのか
■見込み顧客の獲得か
■継続率やLTVの向上か
KGIが曖昧なままKPIを設定すると、評価軸も行動もブレやすくなります。まずは定量的・定性的なゴールを明確にすることが設計の前提です。
■あわせて読む
『LTVとは?マーケティングにおける意味と活用方法』
STEP2:プロセスの可視化と因数分解
KGIを達成するまでのプロセスを可視化し、それを構成する要素を因数分解します。たとえば「年間売上を10%伸ばす」がKGIの場合、その構成要素は以下のように分解できます。
■新規顧客数
■平均購買単価
■リピート率
さらにその「新規顧客数」を生むために必要なプロセスとして、以下が考えられます。
■Web流入数
■CVR(コンバージョン率)
■問い合わせ後の商談化率
このような要素まで細かくブレイクダウンしていきます。この因数分解がKPI設計の精度を決める重要ステップです。
■あわせて読む
『新規顧客獲得戦略とは?成果につながる手法と考え方を体系的に解説』
STEP3:KPI候補の抽出と現実性の検討
次のステップとして、因数分解をもとに、どの指標をKPIに設定すべきかを選定します。このとき重要なのは、「戦略的に意味があり、現場でコントロール可能かどうか」です。
■施策によって変化を生み出せるか
■チームで日々追える粒度になっているか
■現状とのギャップが現実的か(高すぎ・低すぎないか)
KPIは“行動を促す設計”であり、プレッシャーや数字合わせの対象ではありません。「使えるかどうか」でKPIを評価しましょう。
STEP4:モニタリング・改善フローの設計
設計したKPIは、“設定して終わり”ではなく、継続的に振り返り、改善する前提で活用することが大前提です。
■KPIが目標達成に寄与しているかの検証
■結果に対する施策の見直し
■チームでの定期的なレビュー体制
【戦略 → 設計 → 実行 → 改善】のサイクルにKPIがきちんと機能する設計こそが、実務では最も重要です。
KPI設計でありがちな失敗と注意点
KPIは戦略と実行をつなぐ重要な設計要素ですが、設計方法を誤ると、逆に現場を混乱させたり、形骸化を招いたりする原因にもなります。
ここでは、KPI設計において特に注意したい失敗パターンと、その回避のための視点を整理します。
成果指標ばかりで行動に落ちないKPI
KPIを「CV数」「売上金額」など成果そのものに設定してしまうと、施策改善のヒントが得られません。
例えば「CV数を月100件に」とだけ設定されていても、そのCVを生むためにどの行動を強化すべきかが不明確では、施策やチームの方向性がバラバラになってしまいます。
成果指標ではなく、“その成果を生み出すための行動・プロセス”にKPIを落とし込むことが大切です。
KPIが多すぎてチームが混乱する
良かれと思ってKPIを10個、20個と並べてしまうと、かえってどれを重視すべきかわからず、チームの行動が分散してしまいます。
KPIは「最小限で、最大の効果を生む」ものに絞るのが鉄則です。
弊社Oz link(オズ・リンク)では、1〜3指標程度に絞ることを推奨しており、必要に応じてサブKPIで補完する形式を採用しています。
評価のためのKPIになり、現場が疲弊する
KPIが「評価・管理のための数値」になってしまうと、現場は数字を守ることが目的化し、本来の成果追求が後回しになります。
また、「目標未達=叱責」といった雰囲気が生まれると、KPIの信頼性や運用継続も難しくなります。KPIは“行動の指針”であって“査定の基準”ではないという立ち位置で設計・運用することが重要です。
測定できない指標をKPIにしてしまう
「顧客満足の向上」「ブランド好感度の強化」など、定性的で測定が難しい指標をKPIにしてしまうと、進捗判断や改善が困難になります。
こうした定性的な要素は、別の“測定可能な代理指標”に置き換えることでKPI化するのが現実的です。
たとえば以下の代理指標が挙げられます。
■「ブランド好感度」→ SNSのUGC発生数やポジティブコメント率
■「満足度向上」→ NPSや再購入率の変化
KPIには必ず「定期的にトラッキングできる指標」を採用するようにしましょう。
Oz linkが実践するKPI設計の特徴と考え方

Oz linkでは、単に数値を追うためのKPIではなく、戦略との一貫性と、現場が実行に移せる再現性を重視したKPI設計を行っています。
ここでは、Oz linkが多様なプロジェクトで培ってきた設計思想と、実践的なアプローチを3つの視点から紹介します。
目的と戦略から逆算するKPI設計(STP/WHO・WHAT)
Oz linkでは、KPIを設定する前段階としてSTP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)やWHO/WHAT設計を行い、「誰に」「何を」「なぜ届けるのか」という戦略の骨格を明確化します。
これにより、KPIが目的と切り離された単なる数字にならず、「この指標を伸ばす意味」が戦略的に説明できるようになります。
たとえば、「Webリード数」というKPIひとつをとっても、どのセグメントの誰に対してのリードかが明確であれば、施策の精度と一貫性が格段に高まります。
■あわせて読む
『【保存版】マーケティング戦略フレームワーク12選|STP・4P・SWOTを実務で使いこなす方法』
施策ロードマップとの一体設計(ロードマップ → KPI)
Oz linkでは、KPIは単体で設計せず、施策ロードマップとセットで一体設計します。つまり、「この時期にこの施策を行い、その結果としてこのKPIがどう変動すべきか」を時系列で整理します。
この方法により、KPIが現場で“使える”指標となり、月次レビューや週次改善サイクルの中で成果の有無と原因の紐付けがスムーズに行えます。
また、KPIの推移に合わせて次の施策判断ができるため、戦略のPDCAが実行性を持って回る設計になります。
「意思決定に使えるKPIか?」という運用視点で設計
KPI設計において最も重要なのは、「この数字が出たときに、何をすべきかが明確になるか?」という“意思決定に使える指標かどうか”という観点です。
Oz linkでは、KPIを以下のように評価しながら設計します。
■変化があったときに施策判断の材料になるか
■目標との乖離が、次の打ち手につながるか
■担当者が行動に落としやすい粒度になっているか
こうした運用視点を持つことで、KPIは“現場を動かすツール”として機能し、形式だけの指標にならずに済みます。
マーケティング領域におけるKPI設計の具体例
マーケティング活動は多岐にわたるため、領域や施策ごとに最適なKPIを設計することが重要です。
ここでは、Oz linkが実際に支援する中で用いているKPI設計の具体例を、施策タイプ別に紹介します。
例1:リード獲得を目的としたWebマーケのKPI
■目的:新規リードを増やし、営業接点を創出する
■設計例:
・KPI:月間CV数(フォーム送信数)
・サブKPI:LPのCVR、広告クリック率、オーガニック流入数
・運用視点:KPIが下がったときの打ち手(広告訴求変更/CVポイント改善)
施策とKPIが直結しており、改善サイクルを回しやすい設計がポイントです。
例2:コンテンツ施策における定性的・定量的KPI
■設計例:
・KPI:記事単位のPV数、直帰率、滞在時間
・補助指標:記事内CTAのクリック率、資料DL率
・定性的指標:SNSでの言及数、UGCの発生など
数値だけでなく“どんな読後感を持たれているか”など、ユーザーの感情変化を意識した設計が重要です。
例3:広告運用やLP改善におけるKPI指標
■設計例:
・KPI:CPA(獲得単価)、CV数
・サブKPI:CTR、CVR、平均滞在時間、離脱率
・改善指標:ABテスト結果の勝率、ファーストビュー離脱率
KPIだけでなく、結果の要因を探れる中間指標をあわせて設計することで、改善の質が高まります。
■あわせて読む
『集客に効く広告とは?費用対効果を高める戦略と施策を徹底解説』
『Web広告の成果を最大化するコンサル会社とは?選び方と依頼のメリットを徹底解説』
例4:BtoBセールスファネルにおけるステージ別KPI
■設計例:
・KPI(ステージ別)
・リード獲得数(TOP)
・有効リード率・MQL転換率(MIDDLE)
・商談化率・受注率(BOTTOM)
・補助指標:スコアリング精度、メール開封率・クリック率
ファネルを構造的に捉え、それぞれの段階にKPIを分配することで、ボトルネックの特定と改善がしやすくなります。
KPIを活かすための運用体制と改善サイクル

KPIは「設計した時点」がスタートです。継続的にモニタリングし、改善に活かせる体制をつくることで、初めて戦略を実行に落とし込めます。
ここでは、KPIの運用で重要なサイクル設計と、Oz linkが実践する仕組みを紹介します。
PDCA/OODAでKPIを使いこなす
KPIの運用では、PDCA(Plan → Do → Check → Act)やOODA(Observe → Orient → Decide → Act)といった思考フレームが有効です。
■PDCA:事前に立てた計画と指標に対して、定期的に進捗を振り返り改善
■OODA:変化の早い環境下で、観察と状況整理を重視して素早く意思決定
Oz linkでは、施策の性質に応じてフレームを使い分けながら、KPIを軸とした改善をチームに定着させています。
週次・月次でのレビュー体制と可視化ツール
KPIを“生きた指標”にするためには、定期的なレビューと可視化の仕組みが不可欠です。
■週次レビュー:主要KPIの進捗確認と現場からの一次仮説共有
■月次レビュー:全体の動向とボトルネックの特定、次施策の議論
■活用ツール例:Googleデータポータル/スプレッドシート/BIツール(Looker, MotionBoardなど)
Oz linkでは、KPIダッシュボードをプロジェクトごとに構築し、リアルタイムで進捗確認・意思決定ができる状態を整えています。
KPIを現場の「行動指針」として機能させるには?
最も重要なのは、KPIが現場で「何をするべきかを判断するための行動の基準」として機能しているかどうかです。
■KPIが高まった=どこが機能している? → 再現しよう
■KPIが落ちた=どこに課題がある? → 検証・仮説立てしよう
こうした意思決定とアクションが日常的に行われる環境づくりが、KPIの価値を最大化する鍵です。
Oz linkでは、ワークシートや対話フォーマットを用いて、KPIを“数字”から“行動の起点”に変える支援を行っています。
まとめ|KPI設計は戦略の精度と実行力を高める鍵

KPIは、単なる数値管理ではなく、戦略と現場をつなぎ、組織の意思決定と行動を導く指標です。設計の精度を高めることで、目標に向かうスピードが上がり、改善サイクルの質も向上します。
Oz linkでは、戦略設計から施策実行までを一貫して支援する中で、KPIを「現場で使えるか」という視点で設計し、活用と改善まで伴走しています。
数字を“追うもの”から“動かすもの”へ――KPI設計を見直すことは、組織の前進力そのものを見直すことにつながります。
マーケティングに関するお悩みがあるのなら、まずは無料相談にてお気軽にお問い合わせください。
■あわせて読む
『マーケティング戦略とは?意味・STP分析・立て方・成功事例まで徹底解説!』
『コンテンツマーケティングとは?|基本から実践までの効果的な活用法を解説』
『【完全ガイド】マーケティング戦略の立案方法|フレームワークと4ステップ設計術』
『飲食店マーケティング戦略ガイド|集客・ブランディング・SNS活用まで実践事例で解説』
『マーケティング方法を戦略から施策まで体系的に解説|成果を出すための実践プロセスとは?』
『BtoBマーケティングの課題を解決するコンサル会社とは?成功事例と選び方を解説』
『BtoBマーケティングの課題とは?成果が出ない原因と解決の設計ステップ』
『TAM・SAM・SOMとは?市場規模の考え方と違いを図解でわかりやすく解説』
About me
この記事を書いた人

Oz link 編集部
デジタル戦略を中心にクライアントを成功へ導くマーケティングコンサルティングエージェンシー株式会社Oz link(オズ・リンク)。顧客起点の科学的マーケティングを一気通貫で支援することで、企業の持続的な成長を実現します。ブランディングやマーケティング全般、プロモーションや営業活動における課題解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
> ご相談・お問い合わせはこちら> 株式会社Oz link代表取締役のX
> Oz link Group執行役員CMOのX



